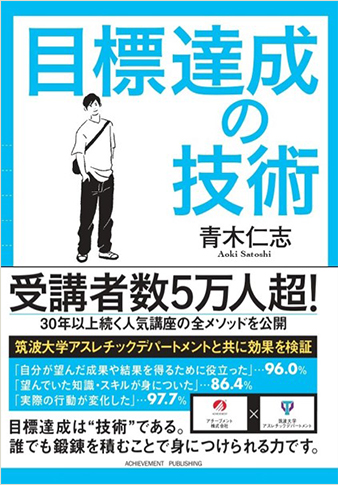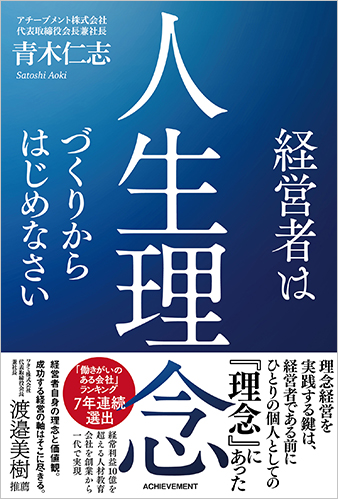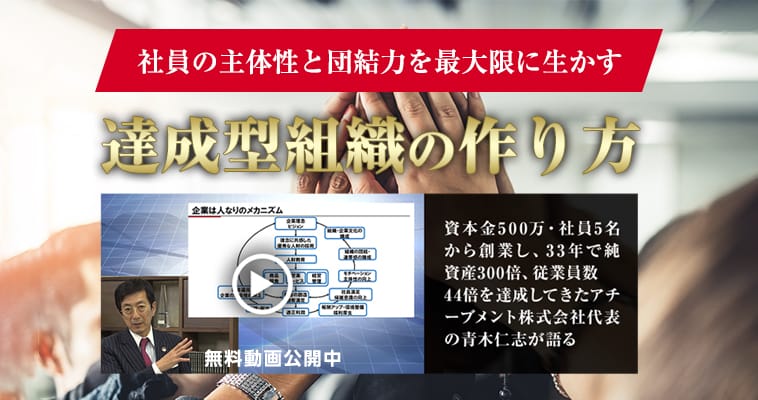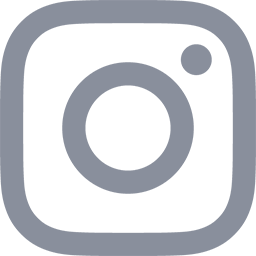-
経済産業省 経済産業事務次官
飯田 祐二氏
-
アチーブメント株式会社 顧問 木俣 佳丈氏
- アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長
青木仁志
「人」の育成こそ「変革」の源泉 日本経済活性化の要諦に迫る
長きにわたって低迷を続けてきた日本経済。近年、国際競争が激化の一途をたどり、日本経済を取り巻く環境はさらに厳しさを増している。しかしここにきて、“潮目が変わる”動きも見え始めた。日本経済の変革を促す抜本的な政策が打ち出され、新たな成長への道筋が示されるとともに、国外でも日本企業に対する評価が高まり、追い風が吹き始めている。そうしたなか、今後の日本の成長を加速させるためのポイントとなるのが人材の育成だ。2023年より経済産業省の事務次官に就任した飯田祐二氏に、日本経済再興への取り組みや目指す方向性などについてお話を伺った。
ミッション志向の産業政策で正のスパイラルを起こす

失われた30年を経て、世界と日本の関係は様変わりしました。2023年のIMF統計データによる世界の名目GDPランキングでは、日本はドイツに抜かれて世界4位に低下しています。国際競争力も1990年代には世界1位でしたが、いまや31位。国家間の競争が今後ますます激しくなるなか、日本の将来を憂う声は多いと思います。
 飯田氏
飯田氏2023年には米国マクドナルドの最低賃金が、20ドルつまり3000円程度であったと聞きました。1990年代前半に内外価格差はというと、日本が高くて外国が安い状況でしたが、ご存じのとおりいまは逆転現象が起こっています。この30年の間に日本は「モノ」も「人」も安くなり、世界における立ち位置も変わりました。

岸田首相は日本のこの30年を「コストカット型経済」と指摘されました。 人への投資や賃金、設備投資、研究開発投資などがコストカットの対象になり、その結果として消費と投資が停滞して悪循環を招いたと。
 飯田氏
飯田氏努力してこなかった訳ではありませんが、結果として負のスパイラルが生じてしまいました。売上原価を抑えて利益を出しても、営業利益に対する設備投資比率や、人材投資も低水準で、将来の成長に対する投資をしてこなかったことが大きな課題でした。

特に大企業の投資は海外に向かっていくことが多く、国内経済への貢献が弱かったように思います。

そうした経緯を踏まえて、経済産業省産業構造審議会の『経済産業政策新機軸部会』では、2021年以来、日本経済のビジョンやその実現に向けた政策についての議論が重ねられていますね。
 飯田氏
飯田氏はい、その新機軸部会で2022年6月に「中間整理」、2023年6月に「第2次中間整理」を発表しました。方向性としては、世界的な社会課題を起点に、新規成長分野やスタートアップへ官民が連携して大胆に投資し、グローバル規模で成長する事業の創出を目指そうというものです。それにより高成長・高賃金化していく「正のスパイラル」を生じさせようと考えています。

これまで以上に国が民間と連携し、経済の活性化を図ろうということですね。
 飯田氏
飯田氏はい。官民連携を強化することで、イノベーションや投資を引き出そうという狙いです。私たちは日本経済変革に向けて、二つの柱を打ち出しました。それが『ミッション志向の産業政策』と『社会基盤(OS)の組替え』です。

それら二つの柱について、詳しくお話しください。
 飯田氏
飯田氏『ミッション志向の産業政策』では、〝社会課題の解決〟と〝経済成長・国際競争力の強化〟の双方を実現するため、「第2次中間整理」で注力すべき8分野を設定しています。その8分野は「炭素中立型社会の実現」、「デジタル社会の実現」、「経済安全保障の実現」、「新しい健康社会の実現」、「災害に対するレジリエンス社会の実現」、「バイオものづくり革命の実現」、「成長志向型の資源自律経済の確立」「少子化対策としての地域の包摂的成長」です。それらの社会課題に対してミッション志向で取り組み、官民連携で投資して、解決するというアプローチを取ります。

具体的にはどのような内容でしょうか。
 飯田氏
飯田氏私は内閣官房GX(グリーントランスフォーメーション)実行推進室の総括室長も兼務しているので「炭素中立型社会の実現」の分野についてお話しすると、今後10年で官民合わせて150兆円の投資の実現を後押しすることにしています。GX経済移行債の発行により20兆円規模の支援を行うこと等によりこの分野の取り組みを支え、GXによる新産業創造や、産業構造高度化を加速していきます。

特定分野においてミッションを設定し、官民で長期的なビジョンや目標、戦略などを共有し、ともに成長させていこうということですね。
中堅企業への支援を手厚くし、成長規模の拡大を図る

2本柱のもう一方、『社会基盤(OS)の組替え』は、どのような取り組みになりますか。
 飯田氏
飯田氏『ミッション志向の産業政策』を支えていくためにも、これからの時代に合った経済社会システムへの組替えが必要です。そうすることで産業構造の変化や、激化する国際競争への対応力をつける必要があると考えています。これについても「人材」、「スタートアップ・イノベーション」、「価値創造経営」、「徹底した日本社会のグローバル化 」、「行政:EBPM・データ駆動型行政」という5つの分野を掲げて注力していきます。

30年にわたる日本経済の低迷の背景としては、産業構造の大きな変化や、生産年齢人口の減少、設備投資の減少など様々な要因が指摘されています。今回の経済産業省の取り組みは、これまでの負のスパイラルを断ち切り、官民を挙げて新たな成長を目指そうという意気込みを感じます。心強いですね。

そうした新機軸に加えてもう一つ着目したいことは、経済産業省が産業競争力強化法の改正案を打ち出し、新たに「中堅企業」の定義を設定したことです。従業員数2000人以下の企業を中堅企業と定義し、地域経済のけん引役とみてサポートしていこうということですが、これは特筆すべきことだと思っています。
 飯田氏
飯田氏製造業の場合は従業員300人以下または資本金3億円以下の企業が中小企業に区分され、これ以外はすべて大企業に区分されていました。この度の改正で中堅企業に該当することになる企業は、中小企業向けの支援を受けられずにいたのです。そうした企業への支援を手厚くし、成長を促すという狙いがあります。

新定義では一部の上場企業を含む9000社が中堅企業に該当するとのことですね。そうした企業を重要視し、支援を強化する理由をお話しください。
 飯田氏
飯田氏大企業は、海外拠点への投資や事業拡大を中心に力を注いできました。それに比べて中堅企業は海外展開を見据えながらも、国内の事業や投資を堅実に拡大し、国内経済の発展に寄与しています。国内への投資や事業拡大がないと、国内の生産性向上や所得アップに結びつきにくいので、こうした中堅企業の実績は日本経済にとって貢献度がとても高いのです。また中小企業に比べて一社あたりの従業員数が多く規模も大きいので、成長すれば取引企業や従業員への波及効果も大きい。賃金引き上げや雇用創出などの効果も望めます。

若い世代の雇用が増え、賃金が上がれば、少子化対策としても有効ですね。支援については、どのようなことを行っていくのでしょうか。
 飯田氏
飯田氏新たな投資や規模拡大、M&A、賃上げ促進などを後押しする税制優遇措置等を講じる予定です。実は日本は、ベンチャー企業・中小企業が中堅企業へと成長し、さらに大企業になっていくという例が少ないのが現状です。中堅企業、大企業に成長していくと、中小企業のときに受けられた手厚いサポートを、受けられなくなるということも一因になっています。中堅企業になっても支援が整っているようになれば、成長への意欲も削がれることはなくなるでしょう。

全日本企業の99.7%を占める中小企業へのサポートについて、経済産業省はこれまでとてもきめ細かく行ってきた実績がありますね。それに加えて、地域経済のけん引役ともいえる中堅企業へのサポート体制が整うということであれば、日本経済の今後の成長に、より期待がもてるようになります。
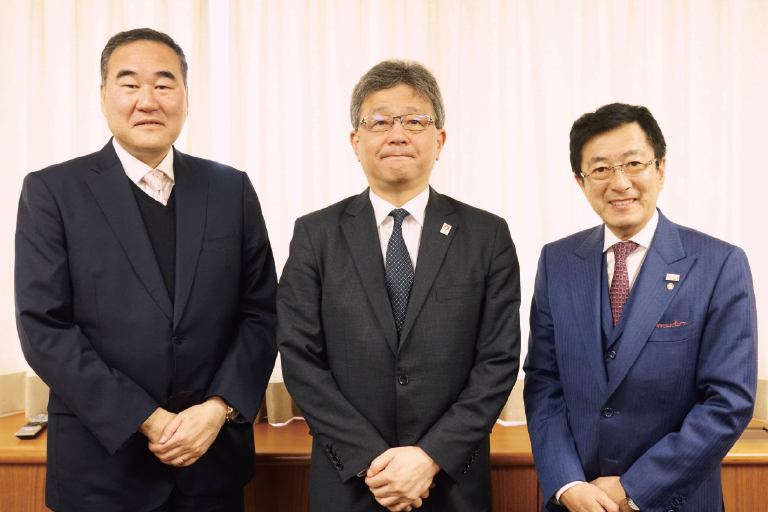
「個」の成長が組織を伸ばし、その連鎖が日本を活性化する

将来に向けた官民挙げての自助努力について心強いお話が聞けましたが、昨今、海外からも日本に対する追い風が吹いています。日経平均株価が続伸し、2024年2月にはバブル経済ピーク時の最高値を超え、その後、初めて4万円台にのりました。株価上昇をけん引したのは主に外国人投資家で、日本企業を見直す動きが大きくなったとみられていますね。

日本に資金が集中しているのは、地政学上のリスクが高まった影響もあるでしょう。とはいえ財務の健全性が高く、ガバナンス改革が進んだ日本企業は評価が高いのも事実ですね。
 飯田氏
飯田氏企業の資本の使い方も変わり、国内の設備投資も増加しています。1991年度に100兆円を超えて以来長らく低迷してきましたが、2023年度は設備投資が再び100兆円を超えるといわれています。

国外からの大型投資もありましたね。2024年2月に台湾の世界的半導体メーカーであるTSMCの熊本工場が開所されました。
 飯田氏
飯田氏はい。そこにも地政学上のリスクを低減しようという狙いもありますが、それだけではありません。日本には半導体の装置や材料で強みをもつ企業が多く、開発・量産拠点として価値が高いと評価された結果でもあります。

工場建設への投資のほか、関連企業の進出、住宅や各種施設の整備、消費の増加など、様々な面で地域経済への波及効果は大きいですね。10年で6兆9000億円を上る経済波及効果があるという試算もあります。
 飯田氏
飯田氏今回のTSMCの件に関しては、数年前から同社を支援できる体制を整え、法改正なども行い、約5000億円の補助金を投じたことが結実しました。こうした取り組みも、先ほど申し上げた新機軸の一環です。

素晴らしい。そうした生産拠点を支える上でも、人材育成の課題はより重要になってきますね。もちろん日本経済をさらに上向かせていくためにも、大切なのはやはり「人」でしょう。
 飯田氏
飯田氏おっしゃる通りです。今回の変革の、最重要な要素だと考えているのが「人材」です。どのような組織であれ、さらには国であれ、やはり「人」の育成が最重要であることは間違いありません。先に申し上げた『社会基盤(OS)の組替え』の5つの目標では、「人材」を第一項目として掲げています。

一般論として人材が大切だということもあるでしょうが、近年のように技術革新が早く、事業構造の変化が激しい時代ならではの事情もあると思います。
 飯田氏
飯田氏はい。技術革新が日進月歩の勢いで進み、社会のあらゆるシーンでデジタル化が進展しています。また脱炭素社会の構築に向けて歩みを速める必要もあり、業種を問わず事業環境は大きく変化しています。そうした変化に対応し、成長に寄与できる人材の確保は急務で、そのためのスキルアップやスキルチェンジなども不可欠です。経済産業省でも850億円の予算を投じ、リスキリングや雇用移動などを一気通貫して支援しています。

教育は国家百年の計。飯田さんがおっしゃるように、急変する時代に対応可能な人材を育てることは、火急の問題なのだと思います。それはすなわち、自分を自ら変化させられる人材が必要だということですね。そのためには人の「内在するモチベーション」を引き出す教育が大事です。一人ひとりが人生の「目的」を見つけられれば、それに向かうための変化に対しても、より積極的になれます。
 飯田氏
飯田氏大いに共感します。私たち公務員の仕事も同じですが、自身の目的と外からの要求が一致したときに、人は能力をもっとも発揮でき、高い成果を実現できると感じています。

私たちが32年間にわたって開催してきた『頂点への道』講座は、上場企業経営者をはじめセールスパーソン、医師、弁護士、アスリートなど、多様な方々が5万人以上受講され、「誰のために」「何のために」という人生の目的を発見されています。そこから経営や事業の運営が変わり、結果的に高収益になっているのです。人生の軸を見つけられるので、そのために大いに学び、自らを変革していけるようになります。

まず組織として 〝こうあらねばならない〟というものに、所属する個が合わせるというケースも見受けられます。ですが、「個」と組織の目指すベクトルが同じであれば、より強い推進力が得られます。リスキリングを行おうという組織にも、そうした観点が大切ですね。
 飯田氏
飯田氏同感です。特に若い世代は以前と比べ、組織への依存意識が薄く、自発的にスキルを高めたい人が増えています。そうした気持ちを汲んでサポートすることや、組織の目的を深く共有することができれば、ウェルビーイングの観点からも良い職場が増えるでしょう。「個」の成長が組織の総合力を伸ばし、その連鎖が日本全体を活性化する。そうなれば理想的ですね。

本当にそう思います。貴重なお話を伺えました。ありがとうございます。

埼玉県出身。1988年、東京大学経済学部卒業後、通商産業省(現経産省)入省。産業技術環境局長や経産省大臣官房長などを経て、2022年に経済産業政策局長兼首席エネルギー・環境・イノベーション政策統括調整官に就任。2023年から経済産業事務次官を務める。